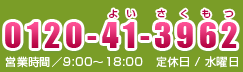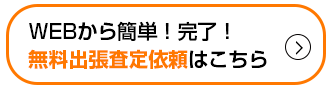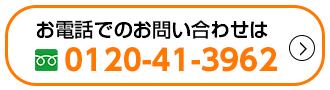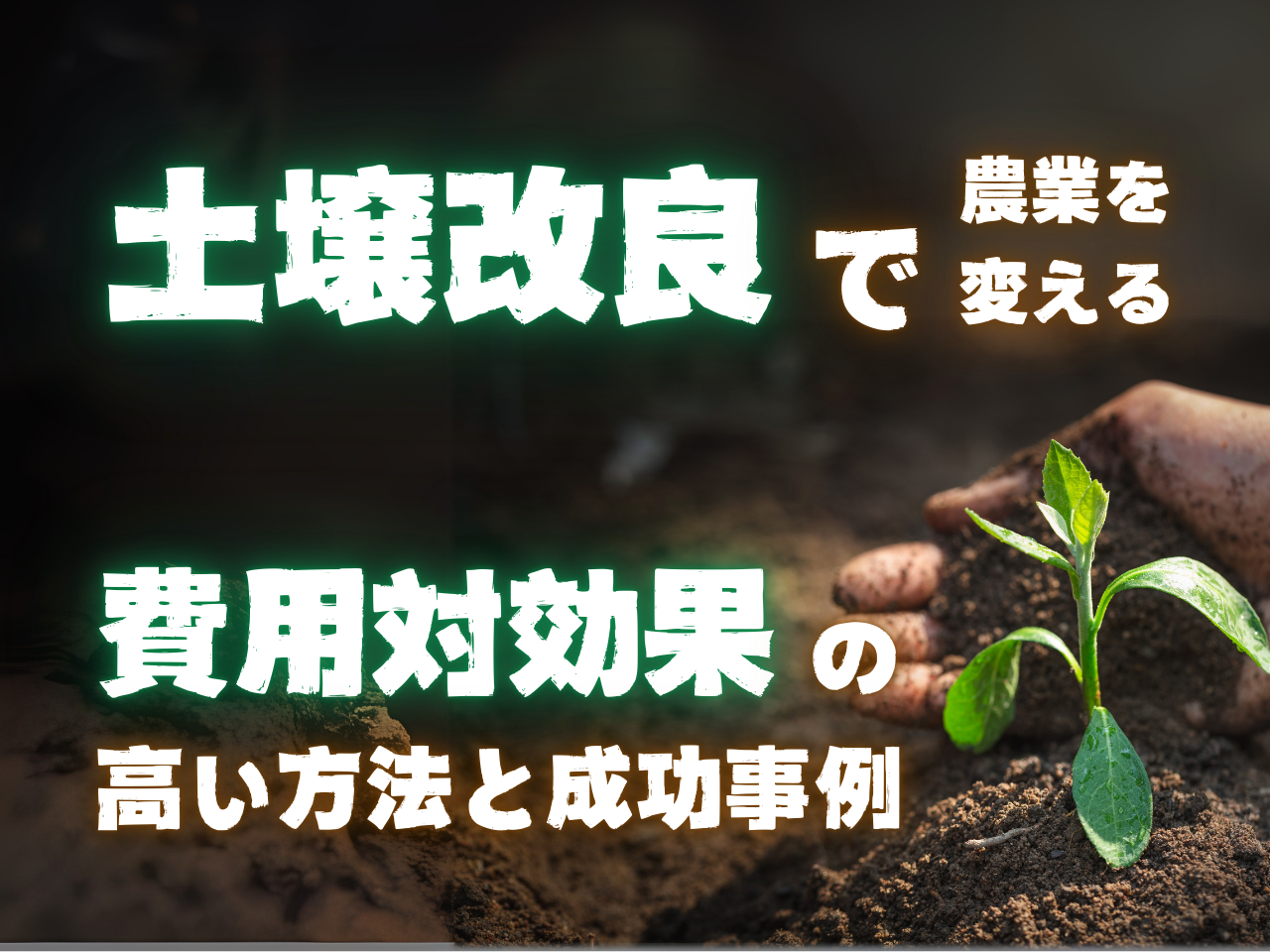
閑散期にこそ行っておきたい土壌改良。土壌改良を適切に行うと、作物の収量や品質を大幅に向上させる可能性があります。
本記事では、土壌改良の基本的な考え方から具体的な実践方法まで詳しく解説していきます。

土壌改良はなぜ重要なのか
土壌改良が必要な理由
土壌改良を行うのには、主に2つの理由があります。
まずひとつは、作物の生育に最適な環境を整えるためです。健康な土壌を保つことで、作物が成長するのに必要な水分保持能力や養分供給能力を持つことができます。根が健全に発達しないと、発育や収量が落ちてしまいます。
例えばトマトの根が十分に発達しないと、果実が十分に大きくならなかったり、糖度が低くなったりします。
次に、連作障害や土壌劣化を防ぐためという理由があります。同じ作物を長年同じ場所で栽培し続けると、特定の養分が不足したり、逆に過剰に蓄積したりします。また、土壌病害虫が増加し、作物の生育に悪影響を及ぼすことがあります。適切に手を加えて土壌改良を行うことで、これらの問題を予防し、長期的に安定した農業生産を可能にします。
例えば、レタスなどの葉物野菜では、連作による根こぶ病の発生を土壌改良によって抑制することができます。
土壌の種類と特徴
土壌には大きく分けて、砂質土、粘土質土、火山灰土の三種類があります。それぞれの土壌タイプには特徴があり、その特性を理解することが効果的な土壌改良の第一歩となります。
砂質土は、粒子が大きく、すき間が多いという特徴があります。排水性が非常に良いため、作物の根が伸びやすいという利点があります。一方で、養分や水分の保持力が低く、肥料が流れやすいという欠点もあります。砂質土での栽培では、有機物の投入による保水性の向上や、少量多回数の施肥が効果的です。
粘土質土は、粒子が非常に小さく、密に詰まっているという特徴があります。養分の保持力は高いものの、排水性や通気性に課題があります。粘土質土は水を含むと粘性が高くなり、乾燥すると固くなるため、作物の根の伸長を妨げる可能性があります。粘土質土での栽培では、有機物の投入による団粒構造の形成や、空気を含ませるように耕すなどの工夫が必要です。
火山灰土は、火山噴出物を母材とする土壌で、日本の各地にあります。リン酸の固定力が強く、作物に十分な養分を供給できないのが難点です。保水性は高いものの、乾燥すると固結しやすい性質があります。火山灰土での栽培では、リン酸肥料の適切な施用や、有機物の投入による物理性の改善が効果的です。
理想的な土壌環境とは
土壌の環境がいいと、作物の生育が促進され、病害虫への抵抗力も高まります。結果として、高品質で安定した収穫が期待できます。例えばイチゴ栽培では、果実の糖度向上や収量増加につながります。
理想的な土壌環境とは、作物の根が健全に発達し、必要な水分と養分を十分に吸収できる状態のことです。
まず、適度な保水性と排水性を備えていることが重要です。水分が多すぎると根が酸素不足になり、少なすぎると養分吸収が妨げられます。適度な水分状態を保つことで、根の呼吸と養分吸収が促進されます。
十分な有機物を含んでいることも重要です。有機物は土壌の団粒構造を形成し、通気性や保水性を向上させます。また、微生物のエサとなり、土壌生態系を豊かにします。
養分の吸収しやすさの観点から、適切なpH値を保っていることも重要です。作物の種類によって値は異なりますが、pH6.0〜6.5の弱酸性が主な目安です。
多様な土壌微生物が活動していることも理想的な土壌の特徴です。土壌微生物は有機物の分解や養分の可給化、病害虫の抑制など、多くの役割を果たします。
土壌改良の主な方法と効果
土壌改良は物理的、化学的、生物的な方法の3つがあります。それぞれのメリットとデメリットをおさえて、状況に合わせて選びましょう。土壌の状態や栽培する作物に応じて、一つに絞ったり、あるいは適切に組み合わせることが重要です。
物理的改良(耕起、混層耕など)
耕起や混層耕など、土壌の物理的な構造を変える方法があります。物理的に空気を含ませたり土の状態を均質化することで作物の根系発達が促進され、養水分吸収能力が向上します。
耕起は、最も基本的な土壌改良方法の一つです。土を掘り起こして空気を入れることで、土壌の通気性や排水性を改善します。結果的に根が健康的に伸びやすくなるほか、土壌中の有機物が酸素と接触することで分解が進み、養分の可給化も促進されます。
必要な耕起の深さや頻度は作物や土壌の状態によって異なりますが、一般的な深さは15〜30cm程度です。
混層耕は、表層と下層の土を混ぜ合わせることで、土壌の均質化を図る方法です。筋質な土壌になることで、根の伸長が促進され、養水分の吸収が改善されます。特に、表層と下層で性質の異なる土壌がある場合に効果的です。
例えば、表層が砂質で下層が粘土質の場合、混層耕を行うことで全体的に均一な土壌を作り出すことができます。
化学的改良(pH調整、養分補給など)
pH調整や養分補給など、化学的に手を加えることで土壌のpH値や養分バランスを調整する方法もあります。作物の養分吸収が促進され、生育が改善することを期待できます。
pH調整は、土壌の酸性度を作物の生育に適した範囲に調整する作業です。多くの作物は弱酸性(pH6.0〜6.5)を好みますが、作物によって最適なpH範囲は異なります。酸性土壌の改良には石灰資材を用います。代表的な資材として、炭酸カルシウム、消石灰、苦土石灰などがあります。これらの資材を適切に施用することで、土壌pHを上昇させ、多くの養分が作物に吸収されやすい状態になります。
養分補給は、土壌中の不足している栄養素を補う作業です。主要な栄養素である窒素、リン酸、カリウムのほか、カルシウム、マグネシウム、微量要素なども必要に応じて補給します。土壌診断の結果を見ながら適切な量と種類を選択することが重要です。
生物的改良(有機物投入、微生物活用など)
有機物の投入、有用微生物の活用など、生物のはたらきによって土壌中の微生物活動を活性化させる方法もあります。土壌内での養分循環が促進し、根の健全な発達や収量増加にもつながるでしょう。
有機物の投入は、堆肥や緑肥などを土壌に加える方法です。有機物は土壌微生物のエサとなり、活動を促進します。微生物の活動が活発になると、有機物の分解が進み、養分の循環が促進されます。代表的な有機物資材として、牛糞堆肥、豚糞堆肥、鶏糞堆肥、バーク堆肥などがあります。
有用微生物の活用は、土壌に有益な微生物を追加する方法です。例えば、根粒菌や菌根菌などの微生物を利用します。これらの微生物追加で、養分の可給化や病害抑制などの効果があります。市販の微生物資材を利用する方法もありますが、適切な土壌環境を整えることで自然と有用微生物が増殖することもあります。
土壌診断はなぜ土壌改善に重要なのか
土壌診断の主な目的は、どんな改良をしていくべきか明らかにすることです。現在の土壌の問題点や不足している要素を特定することで、適切な改良方法を選択することができます。
例えば土壌中の養分含量を知ることで、足りない養分のみを施すことができます。コスト削減と環境負荷の軽減につながります。
また、定期的に土壌診断を行なっていくことで、収量と土壌環境との関係性を分析し、改善のために何をしたらいいかを考える助けになります。

環境別の土壌改良の注目ポイント
作物によって好む土壌環境が異なるため、栽培する作物に応じた土壌改良が必要です。ここでは、主要な農業環境ごとの土壌改良テクニックを詳しく解説します。
水田の土壌改良
水田土壌は、湛水期間中に酸素が不足します。この状態はイネの生育にとっては必要ですが、過度の還元は有害物質の生成につながる可能性があります。そのため、毎年土づくりの際に土壌改良を行っていくことが重要です。例えば、稲わらは収穫後にすき込み、分解を促進させることで、春先の悪影響を避けることができます。
水田土壌改良の主なポイントは以下の通りです。
1.排水性の改善
2.有機物の投入
3.ケイ酸質資材の施用
4.土壌pHの管理
畑作における土壌改良
畑作では、作物の種類に応じた土壌改良が重要です。栽培する作物が多いなら、それぞれの特性ごとに区分けして土壌を管理しましょう。
畑作物は水田作物と異なり、常に酸素が必要な好気的環境で生育します。そのため、通気性や排水性の確保が特に重要となります。畑作における土壌改良のポイントは以下の通りです。
1.有機物の投入
2.pH調整
3.深耕と心土破砕
4.輪作の実施
5.土壌診断に基づく施肥設計
果樹園の土壌改良
果樹は植付け前の土壌改良が特に重要です。一度植栽してしまうと、大規模な土壌改良が困難になるためです。もちろん、植え付け後に継続して表層などで土壌改良のためにできることはあります。
果樹は深根性の作物が多いため、深層土の改良にも注意を払う必要があります。例えば、バックホウなどの重機を用いて深耕することで、堅密層を破壊し、根の伸長を促進できます。
果樹園の土壌改良における主なポイントは以下の通りです。
1.深耕
2.排水対策
3.有機物の投入
4.pH調整
5.土壌改良資材の活用
6.草生栽培の導入
連作障害対策としての土壌改良
連作障害は、同じ作物を長年同じ場所で栽培し続けることで発生する問題です。この連作障害を予防していくには、土壌改良を行わざるを得ません。ここでは、連作障害の原因や症状、そしてその対策としての土壌改良方法について詳しく解説します。
連作障害の原因と症状
連作障害の主な原因としては、特定養分の過度の吸収や蓄積、土壌病害虫の蓄積、作物が分泌する生育阻害物質の蓄積などが挙げられます。
連作障害の症状は多岐にわたりますが、一般的には生育不良、収量低下、品質劣化などが現れます。具体的には、葉の黄化や萎縮、根の褐変や肥大不良、果実の小玉化や糖度低下などが観察されます。また、作物によっては特有の病害が発生することもあります。
まず特定養分が過度に蓄積、あるいは不足すると、土壌中の養分バランスが崩れ、作物の生育不良や品質低下を招きます。
土壌病害虫の蓄積は、特に深刻な問題です。同じ作物を栽培し続けると、その作物に特有の病原菌や害虫が増殖しやすくなります。
作物が分泌する生育阻害物質の蓄積も無視できません。多くの作物は、根から様々な物質を分泌しますが、中には自身や近縁種の生育を阻害する物質(アレロパシー物質)も含まれています。この阻害物質が土壌中に蓄積すると、他の作物の生育に悪影響があります。
連作障害は、単に肥料を増やしたり農薬を散布したりするだけでは解決できません。根本的な土壌環境の改善が必要です。
解決方法としての輪作とその実施方法
輪作は連作障害を防ぐ最も効果的な方法の一つです。異なる作物を年間で計画的に栽培することで、土壌環境を健全に保つことができます。輪作体系を構築する際は、以下のポイントを考慮します。
基本として、異なる科の作物を組み合わせます。例えば、ナス科→マメ科→アブラナ科→ウリ科といった順序で栽培することで、各作物の特性を活かして土壌環境を改善できます。
根の深さが異なる作物を組み合わせることも効果的です。浅根性作物と深根性作物を交互に栽培することで、土壌の異なる層を利用し、養分の偏りを防ぐことができます。例えば、浅根性のレタスの後に深根性のニンジンを栽培するといった具合です。
多肥性作物と寡肥性作物を交互に栽培することで、土壌中の養分バランスを効率的に保つこともできます。例えば、多肥性のキャベツの後に寡肥性のマメ科作物を栽培するといった方法が考えられます。
輪作は多面的な観点から計画を立てなくてはなりませんが、より自然なやり方で持続可能な農業生産が可能となります。
緑肥作物の活用法
緑肥作物は土壌改良と連作障害対策の両面で効果的です。緑肥作物を栽培し、土壌にすき込むことで様々な利点が得られます。
すき込んだ緑肥は土壌中で分解され、腐植となって土壌に蓄積されることで、土壌の保水性、通気性、保肥力が向上します。例えば、ソルガムやエンバクなどのイネ科緑肥作物は、土壌に大量の有機物を供給します。
ヒマワリやソルガムなどの深根性の緑肥作物を利用すると、根が深くまで伸長することで土壌を膨軟にし、作物の根の伸長が促進され、養水分の吸収が改善されます。
マリーゴールドやクロタラリアは線虫抑制効果があり害虫予防に役立ちます。またマメ科の緑肥作物(レンゲやクローバーなど)は窒素固定能力があり、土壌に窒素を供給します。イネ科の緑肥作物は炭素率が高く、すき込み後の窒素飢餓を引き起こす可能性があるため注意が必要です。
タイプ別:おすすめの土壌改良資材
効果的な土壌改良を行うためには、適切な資材の選択と使用が重要です。ここでは、おすすめの土壌改良資材とその使用方法を詳しく紹介します。
有機質土壌改良資材
有機質土壌改良資材として堆肥、バーク堆肥、ピートモスなどがあります。
堆肥は、動植物性の有機物を発酵させたものです。牛糞堆肥、豚糞堆肥、鶏糞堆肥などがあり、それぞれ特徴が異なります。牛糞堆肥は分解が遅く、土壌改良効果が長続きする一方、鶏糞堆肥は養分含量が高く、即効性があります。
バーク堆肥は、樹皮を発酵させたもので、保水性と通気性を改善します。特に砂質土壌での使用が効果的です。
ピートモスは水分保持能力が高く、土壌の膨軟化に効果があります。酸性度が高いため、使用の際はpH調整が必要です。
無機質土壌改良資材
無機質土壌改良資材としては石灰資材、ゼオライト、バーミキュライトなどがあります。これらの無機質資材は、有機質資材と併用することでより効果的な土壌改良が可能となります。例えば、石灰資材と堆肥を同時に施用することで、pHの調整と有機物の補給を同時に行うことができます。
石灰資材は、pH調整とカルシウムの供給に効果的です。苦土石灰、消石灰、炭酸カルシウムなどがあり、土壌のpHや作物の種類に応じて選択します。
ゼオライトは、保肥力の向上と重金属の吸着に効果があります。特に砂質土壌での使用が効果的です。
バーミキュライトは、保水性と通気性の改善に効果があります。特に育苗用土や鉢植え用土としての利用が多く、土壌容量の10-30%程度を混合します。
微生物資材
近年、土壌改良資材として注目を浴びている微生物資材は、根粒菌、菌根菌、枯草菌などを含みます。効果としては、例えば根粒菌を含む資材はマメ科作物の窒素固定を促進し、菌根菌を含む資材はリン酸の吸収を助けます。
一般的に種子や苗に与えたり、土壌に直接施用したりします。例えば、根粒菌資材は、マメ科作物の種子にまぶして使用することが多い資材です。
微生物資材の効果は環境条件に大きく左右されるため、pH、水分、温度などを整えることが重要です。また、化学農薬と併用すると土壌微生物に悪影響を与える可能性があるため、
土壌改良を農機具で効率化するならあぐり家へ
土壌改良の効果を最大化するには、農機具があると便利です。例えば、深耕用のプラウやロータリー、堆肥散布機、石灰散布機など、土壌改良に欠かせない機械など、他の作業でも使う農機具が活躍します。
もし高額だからこれまで使っていなかったものがあるなら、ぜひあぐり家の販売ページをご確認ください。あぐり家は農機具を専門に買取・販売しています。気になるジャンルから商品を探してみて、予算と合うかチェックしてみませんか?

使っていない農機具がある場合、買取査定をいただければ無料で査定に伺います。中古での購入の原資にもしていただけるので、倉庫の中をぜひお探しください。

株式会社K・ライズホールディングス 営業本部
桑原 翔
(Kuwahara Tsubasa)
1987年4月生まれ、趣味はパソコンいじりと音楽全般。専門商社の営業職とSaaS(クラウド)のカスタマーサクセスやマーケティング業務を経て、K・ライズホールディングスに入社。営業本部所属で、主に「國丸」「あぐり家」「RiZ」を担当し、各事業のサイトのディレクションやオンラインマーケティングのほか、オフラインマーケティングを担当。